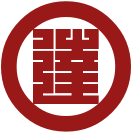これまで「マスター」と「達人」という二つの概念の相違について考えてきた。似て非なるこの概念についてねちっこく話を続けたのは、これが中国語学習プランを作成する上で最重要項目の一つとなる「習得目的」に直結するからだ。
まずは達人を目指すのか否か。もし達人を志すならば、人生を中国語に捧げる覚悟が必要になる。そのつもりがないのなら達人になろうなんていう考えは持たない方が良い。達人になるつもりがなければ「マスター」すれば良いだけの話だ。これなら話は(場合によってはだが)簡単である。自分に必要となる中国語能力を身につければ良いのだ。
似て非なる「達人」と「マスター」
通訳でもない限り、必要となる中国語力を身につけるのはそれほど難しいものではない。必要となる能力は切迫性があるため、なんとしても早く身につけようという強い学習動機が働くからだ。およそ継続を要求される習い事(語学もその一種)を身につけるには、強く且つ継続的な学習動機の存在が大きな意義を持つ。この点を考えると、すぐにでも生活や仕事上必要になるというのは強力な動機付けとなるのだ。
また、必要となる中国語というのは実際に使用する中国語でもあるので、その範囲内については日を追うごとに熟練していく。加えて日常的に且つ頻繁に使用するので、その範囲において記憶の定着度が著しく高く、退化しにくいという利点もある。
これは達人を目指す学習者と比較するとよりわかりやすいかもしれない。達人を目指す学習者は、一生のうち一度出会うかどうかもわからないような語彙や表現まで覚えようとするが、覚えたところで日常使わないのですぐ忘れてしまう。一つや二つという話ではなく、何百何千何万という言葉を頭に入れようとしているのだから忘れるのも無理はない。生理現象なのだ。彼らはこの自然の摂理に逆らって学習を進めていく。言わば上流に向かって泳ぐようなものだ。必死に手足を動かしても前にはほとんど進まず、逆に少しでも気を抜くと、あっという間に下流へ流されていく。
この喩えを借りるのならば、必要になる中国語力だけ身につけることは、上流から下流に向かって泳ぐようなものだ。日ごろから使用しているので、特に復習などしなくても自然と記憶が固まっていき、熟練していく。
まずは中国語「マスター」から
より具体的な例を出してみよう。例えば、夫の中国赴任で中国についてきた婦人の場合、家から一歩足を踏み出せば即中国語空間が広がっているのだ。その気になれば日本で学ぶ学習者よりもずっと日常会話の上達が早くなる。もちろん、日本人グループで固まってしまっては話は別だが。
日常の業務の中で中国語を使うビジネスマンなら、業務の中で使う中国語については上達が早くなる。仕事という避けて通れない差し迫った理由があるのだから当たり前だ。もっとも、ビジネスの場合は比較的低い中国語力でも対応できる仕事もあれば、かなり高度な中国語力を要求されるものもあるので、一概には言えないのだが。
一方、現役大学生で「中国語を就職の武器」に、と考えているような場合、履歴書に書き込める中検のような資格試験で一定の級を取得するのが当面の目標となろう。このようなケースでは中国語が即必要になるという訳ではないので、動機付けは相対的に弱くなる。また、学習プロセスも体系的なもの、いわゆる典型的な「お勉強」型になりやすい。覚えたものを即実践で使うことができないので、忘却との戦いを強いられることとなる。ただ、この場合でも資格試験取得に目的を絞り、資格試験で問われる部分のみに集中するという方法もある。学習項目を減らすことで、学習効率を上げるのだ。
この他、学術で中国語が必要になる人と、ビジネスで中国語が必要になる人では学習の重点が異なってくる。学術の場合は読み書きに比重が置かれるが、ビジネスの場合は相対的に会話の重要性が高くなる。また、単に日常会話ができればよし、とする人と、通訳になりたい、という人では、必要になるレベルに天地の開きがある。前者なら学習法を選り好みすることができるが、後者では効果効率を優先して学習プランを構築しなければならない。だからこそ、必要になる能力がどの分野のもので、どの程度のものなのか事前に把握しておくことは、中国語を「マスター」する上で非常に重要になるのだ。
中国語をツールとして割り切って考えれば、とりあえずは必要最低限の中国語力を身につければ良いのだから、必要ない分野項目についてはバッサリと切り落としてしまうのだ。量が少なくなれば負担も大幅に軽減され、またゴールも近くなる。ゴールが近くなれば挫折の可能性も低下する。良いことづくめなのだ。
もし中国語を使用する切迫した理由があるのなら、とにもかくにもツールとして使い物になるレベルを目指すのが中国語習得の最短コースとなる。その上でさらに上を目指すかどうかは本人次第だ。ただ、少なくとも、そのときのあなたは、すでに中国語を「マスター」した中国語使いなのだ。